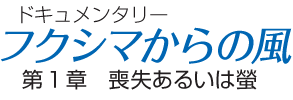作品内容
作品の前提として、福島第一原発、事故後の飯館村の動揺が素描される。
村の体育館で行われた(4月30日)東京電力による説明会から始まり、一般住民への村長からの避難勧告。
そして、ある畜産農家の牛の処分風景へ。そこでのインタビューにより、個人の抱える苦悩と希望が、浮き彫りにされる・・・。
タイトル「第一章・喪失あるいは蛍」
ここで第一章としたのは、いかに描かれる人々の春から夏へを一区切りとしてまとめ上げ、今も収束のつかない現実にできるだけ遅れをとるまい、と考えたからである。(現在も秋から冬への撮影はつづいている。)
又、この作品がフクシマの現実の一断面にすぎないことは言うまでもない。恐らく、この作品が公開される時期には、さまざまな角度から捉えられた ドキュメンタリー作品が数多く現れるだろう、それぞれの作品が相互に補い合い、第二章でもあり、三章でもあり得るという意味もこめて付けられている。
先ず登場する飯館村の昌基さんは、自分の広大な山に山草や薬草を移植し、育てながら研究している84歳の老人である。
その植物への好奇心と熱心さ、そして若々さには驚かされる。偶然見つけた発根剤を使って、放射能の除染を試みるつもりだと言う。
傍らにはいつも笑顔の奥さんが寄り添っているが、そんなふうに、好きなことを続けて来た自分の人生は、女房と二人三脚での歩みでなければやって来れなかったともらす・・・。
次に登場するのは、奥さんを5月に亡くしたばかりの常次老である。奥さんは第一原発のすぐ近くの双葉町の病院に入院していたと言う。今の常次さ んの唯一の楽しみはドブロク作りである。(朝から飲んでいることもある)。常次さんは、長年住みなれた川内村の家を離れる気はないようだ。むしろ、後を継 いでくれる人を探している。そんな常次さんの庭の木にモリアオガエルが卵を産みつけた。・・・・・・・
同じ川内村の近くの山奥に、獏原人村がある。1970年代から仲間と自給自足の村造りを始め、現在はマサイさん夫婦二人だけて、ニワトリを 飼い自然卵で生計を立てている。太陽光発電で暮らし、ギターを友とし、年一度の夏祭り(満月祭)を催す。第一原発の20kmラインに住んでいるこ とから、事故以前から線量計で放射能測定をつづけていたそうだ。
自然相手の一見のどかな生活であるが、マサイさんの口から発せられるのは、国への不信であり、現代社会に対する批判であり、そして、私たちは今回の原発事故をどうとらえていくべきか?という自分自身に向けての鋭い問いかけである。・・‐‐
最後に、締めくくりとして、3年前に夫を亡くした小林さんが登場する。かつて夫と暮らしていた飯館村の、どこよりも美しい谷間を取り戻した い、という夢が語られる。・・・
エピローグは風吹く飯舘村の人気のない風景である。過去(数力月前)にその風が、そこに住む人々にくまた私たちに)もたらしたものは何なのか? そして、これから、そこから吹くだろう人々の思いを乗せた風は、未来にどんな変化をもたらすのだろうか?
もう一度、登場人物の一人一人の生き方に想いをめぐらし、遠く新たな時代を見据えてほしい、という願いをこめて、この作品は終わる。
作品意図
はじめに断っておかなければならないのは、この作品はあくまでも″映画作品″として作られている、ということである。つまり、映像を通し、 そこに映っている人々の姿、生の言動から、何ものかを自ら感じとり、想像をめぐらし、考えてほしいとする映像体験としての作品ということであ る。故に、外からの言葉による〈説明的)ナレーション。話しことばへの字幕などは極力排除されている。
昨今のドキュメンタリー作品はことさら分かり易すさを強制されているかに見える。TVのそれの影響によると思われるが、そこにあるのは、日 と耳の積極的な想像力の枯渇である。だから又逆に、喜怒哀楽においても、いかにもの、ドラマチックな展開を見せるもの、明白な主張の開かれる ものが好まれる、という傾向になる。どちらも、受け身のままでいても、なんとなく手ごたえを感じさせてくれるからであろう。
現代社会の大きな弊害の一つは、人々から想像力と思考力(問う力)を奪い、その生き方を個性のない(目覚めさせない)、一様化した平板なも のにしてしまうことにある。何事も他人任せに迎合し、たやすく即解答のみを求める安易な姿勢である。まさに、そうしたことが、原発をいつの間 にか容認してしまう私たちの心性と繋がっているはずなのである。
この作品に登場するのは皆個性豊かな生き方をしている人ばかりである。けれど、他の生き物への関わりにおいて、自然との接し方において、他者との、伴侶との絆において、慈しみ、思いやり、共に生きていこうという姿勢はどこか共鳴し合い、四重奏を奏でている。
そして、作品中のマサイ氏の口にする、人に道を譲るという小さな行為が、大きな社会の動きと決して無関係ではない、という言葉のように、そ れぞれ、その人なりの生き方の有り様の一つ一つが、原発に象徴される現代の肥大化した科学文明社会に問いを発している。その声を確かに聞き、 その姿勢を見るためには、じっと眼を凝らし耳をそばだて、想像力の翼を奮い立たせねばならないだろう。映画を見るように。
制作メモ
2011年4月30日 。 とにかく福島がどんな状況にあるのか ?
実際に行って自分たちの目で確かめてみたい、ということで集まった 3名 (「 六ヶ所みらい映画プロジェクト」) が飯舘村 〜南相馬〜川内村 〜いわき市など、二泊三日の行程で現地に足を踏み入れたのがそもそもの始まりである。
その時は撮影を担当した加藤監督は、川内村の獏原人村に関心があったため、出向く気になったと言う。 自分が監督する気は全く無かったが、現地で出会った人々の熱い視線、無理にも笑顔を絶やさない村人の話しぶりが、帰京後もずっと脳裏を去らなかった。
当初「 六ヶ所みらい映画プロジェクト」 は青森中心に記録をまとめる方針だったが、原発事故により、青森に関しては島田恵監督 、福島に関しては加藤監督が担当するというように変わっていった。現在ではほぼ別々のプロジェクトとなっている。
加藤監督が迷いをふっ切り重い腰を上げるのに数週間を要したらしいが、その間、第三者からカメラとテープが用意され、東北自動車道が無料とな り、自分の部屋の片隅にいつもビデオカメラが入ったバッグがあるのを見るにつけ、何かすべてが撮影を始めるよう促しているような、 自分のやる気だけが試されている気がしてならなかったそうである。これだけお膳立てされながら、尻込みし躊躇しているのはなぜなのか?毎日何度となく自問していたという。
では、撮影行を開始するに当たって、自分なりに思いをハッキリ出し得たのだろうか。「否」だったと言う。今でも、「自分はフクシマに呼ばれたの だ・・・」としか言いようがないそうだ。創作メモ曰く、「その時、その人々に見えたのが、苦しみや悲しみだけだったなら、私はその人々にカメラを向ける気 になれなかったであろう・・・私がそのときであった人々に見たのは、言いようのない不気味な不安、苦境の最中にあって、(それを跳ね返すような)明る さ、(きっと乗り越えていくだろう)強靭さとしなやかさ、そして自分なりの生き方を通しての自然とにじみ出ている人間的な魅力と言ったものだった。」そう したものだったからこそ、逆に人々の印象深く、気になり、ひきつけられるように福島へカメラとともに通い始めたのであろう。
製作資金のめどは無かったが、監督のかつての仕事仲間、友人などの協力を得て、青森〜福島を何度も往復する形で撮影が進められた。
作品のエンディングタイトルで個々のパート部を特定しなかったのは、極小のスタッフ編成のため、一人何役も兼ねることが多かったからで、あえて記せば次のとおりである。
プロデュース・雑用=中川登三男、 監督・撮影・構成=加藤鉄、 編集・撮影=高田稔、 撮影=内藤雅行、 整音=吉田茂一
その他「六ヶ所みらい映画プロジェクト」のスタッフ、現地の多くの協力者により2011年11月に完成された。